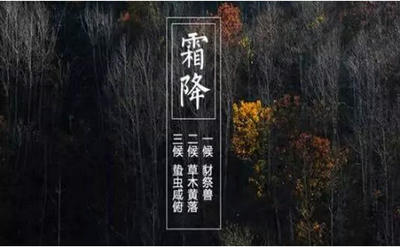燕京雑考@ブログ版
中国・北京の歴史、風習を紹介。一日一つを目指します。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

寒露の七十二候は
一候: 鴻雁来賓(鴻雁、来賓す)
二候: 雀入大水為蛤(雀、大水に入り蛤となる)
三候: 菊有黄華(菊に黄華有り)
鴈が北から群れでやってくる、雀をあまりみかけなくなる、菊が咲く季節です。
参考までに白露の日本の七十二候は
初候:「鴻雁来」(こうがんきたる)
次候:「菊花開」(きくのはなひらく)
末候:「蟋蟀在戸」(きりぎりすとにあり)
~>゜)~<蛇足>~~
「雀入大水為蛤」についてですが、
なぜ雀が蛤になると想像したのかというと、
寒くなってきたころ、雀を見かけなくなり、同じ時期に蛤がたくさん出てきたので、色柄がにていたこともあり、雀が蛤になったのだろうと、昔の人は考えたのだそうです。
寒露の画像は百度百科から

秋分の七十二候は
一候: 雷始收声(雷すなわち声を收む)
二候: 蟄虫坯戸(蟄虫戸を坯す)
三候: 水始涸(水始て涸る)
入道雲の季節が終わり、虫たちが冬支度をはじめ、田畑の水を落とし収穫を始める季節です。
参考までに白露の日本の七十二候は
初候:「雷始收声」(かみなりすなわちこえをおさむ)
次候:「蟄虫坯戸」(むしかくれてとをふさぐ)
末候:「水始涸」(みずはじめてかる)
~>゜)~<蛇足>~~
積乱雲の季節も終わり、本格的な秋到来の季節です。
秋分まで30℃越えの日がつづくのも温暖化が言われている今日では不思議はないのかなと思います。
白露の画像は百度百科から

白露の七十二候は
一候: 鴻雁来(鴻雁来たる)
二候: 玄鳥帰(玄鳥帰る)
三候: 群鳥養羞(群鳥羞を養う)
ガンが飛来、ツバメが南方に帰り、鳥たちが食べ物を蓄える季節です。
参考までに白露の日本の七十二候は
初候:「草露白」(くさのつゆしろし)
次候:「鶺鴒鳴」(せきれいなく)
末候:「玄鳥去」(つばめさる)
~>゜)~<蛇足>~~
七十二候は鳥で表現しているものが多いと改めて思いました。
ガンが来たから飛来、ツバメが南に帰る季節。
そして秋の実りから鳥たちも冬の食料を蓄えるのですね。
白露の画像は百度百科から

処暑の七十二候は
一候: 鷹乃祭鳥(鷹すなわち鳥を祭る)
二候: 天地始粛(天地始めて粛む)
三候: 禾乃登(禾、すなわちみのる)
鷹は獲物を狩って持ち帰えるようになり、空も地も涼しく、穀物が実る季節です。
処暑の日本の七十二候は
初候:「綿柎開」(わたのはなしべひらく)
次候:「天地始粛」(てんち、はじめてさむし)
末候:「禾乃登」(こくものすなわちみのる)
~>゜)~<蛇足>~~
「祭鳥」ですが、いろいろ調べたところ、
鷹はこの時期に、鳥は狩ってもすぐには食べず、
人間がとりあえず神仏ご先祖様にお供えするようにするとかなんとか....
それを「祭鳥」というそうです。
鷹についてちょっと調べてみたいと思いました。
処暑の画像は百度百科から