燕京雑考@ブログ版
中国・北京の歴史、風習を紹介。一日一つを目指します。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
西湖より包頭まで 6 包頭行 -05 墩台の連互
八達嶺から元来た道を下るのは早い、馬よりも歩く方が楽だ。30分で青龍橋駅に達する。
汽車にここでV字に往っ戻って八達嶺隧道道の方へ登るのである。
駅の一方に詹天祐の銅像と大總統の頌給の碑がある。
侯車室で卵子やサイダーを取る。
やがて午後2時16分発の汽車にて北に向う。
隧道は長35080尺もっとも長い。
出た所が嶺外の岔道城の要塞である。
見上ぐればこの山にもあの山にも、古代城壁のルーインらしいものがある。
まだ城壁らしい形をしたものの中に民人の居住せるものが居り
あるいは磚瓦、あるいは土壘のようなものが幾筋となく目につく。
いずれが古いかわからない。
康莊までくると一望の沖積平野である。
窓から南西の山巓を見ると、長蛇のごとき城壁が二筋走つている。
平野は永定河の支流で予想外に広漠たるものだ。
見渡すかぎり高粱のよくできた畑地である。
やがて水の清んだ大きい河を通る。
中々大きいが、でも支流の支流である。
懷来はこの支流々域の中心である。
南方永定本流の方を見ると緑樹蒼々として鶏犬の声互に聞ゆといふ風である。
站頭に林檎を売る漢人の声はなはだ喧しい。
粗末な葛籠に林檎を入れて積出している。
仲仕の数も2、30人は見うけられて中々盛んである。
さてここからさきにゆくと沖積層はいつか黄土層にかわって、
所々に小さい砂川があり、黄土を浸蝕して断崖を作くれるが多い。
黄土の表面は粟、高粱、唐辛など豊作である。
土木駅につく、站南4里にしてかの有名な土木城がある。
正統十四年にエセン入冦、英宗親征して大同に至り、師を班し、
ここでエセンに追擊され、大敗遂に捕虜の憂目あったところだが、
今日ではこの平野はすべて漢人の部落で、たしかに稲田だと思はれるものまである。
豆といい粟といい農業おおいに開けている。
30支里を西して新保安にくると一面の水田に稲が黄熟している。
ふと平地の上を高10メートル内外方5間がほどの土の塔がある。
これはと気を付けると長城以北の山や野のぽつりぽつりとある。
新保安以後はその数いよいよ多く、1支里ごとに作くられ、
山の尾にあれば麓にもあり、小高い岡にあれば低い畑にもある、
これが烽火台たと気がつく、数の多いのに驚く、
ところがこれかどこまでつづくかというと、ほとんどこの汽車道の行くさきざきにあって、
張家口から大同、豐鎭をへて紅砂壩駅までおよそ400キロメートルの沿線に連亘しているのだ。
長城には36丈毎に方形の墩台があるが、この烽台もまた同じ日的で、敵人の来冦を報じかつ防御するところのものである。
さきにのべた漢代に、
「匈奴が句注に入るや烽火甘泉に通じ、数ならずして漢兵至る」とあるのも、
かかる通報機関のあった事を語るもので、
『唐六典』には「舊關内河東河北皆置烽」とあり、「烽と烽と相去る三十里」とあり。杜甫の詩にも「候火雲峯峻、懸軍幕井乾」というがある。
楊烱は「烽火照西京、心中自不平」と歌っている。
しかし今目前にある烽台はさほど古いものでなくて、
多くは明の成化・嘉靖時代のものであるらしい。
余子俊の議によれば「毎一里築立墩台一座、毎座四面根脚各闊三丈高三丈」とあって
上方に6尺の部屋があり、下に1丈からの深い濠をめぐらしてあった。
工人500、土近ければ10日にして1座を作り得るから、
1万人が1ヶ月かかると60座はできる。
「1座10人ずつの守備兵を置き、兵糧は常に1ヶ月の水と米とを貯えろ」とある。
で今見るやうな数の多い墩台ができたのである。
古へは日中には烟を出し、夜中は火を点じてその火の数で賊の多少を報じたのである。
しかし明代には烽火の外に長竿を立て、これに紅燈を吊るしたらしい。
その紅燈の製法まで『山西通志』にのっている。
普通長城の巨工なるを唱うるが城外更にこの墩台の連互を考うるとき、
漢人のいかに苦心したかがわかる。
おだやかに張子容の詩を吟じて、当時の労苦をねぎらわとするもの、あに予一人のみならんや。
平沙落日大荒西 隴上明星高復低 孤山幾處石烽火 戰士連候皷聲と。
~>゜)~<蛇足>~~
わかりやすくするため、原文の以下を変えました。
也先: エセン
PR
西湖より包頭まで 6 包頭行 -04 万里長城 前編
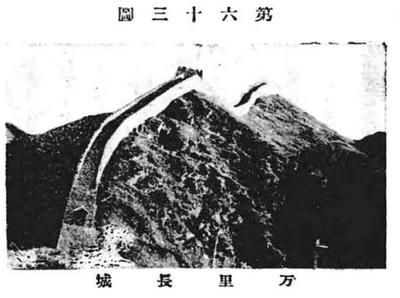
普通内門を通って外門に進み、外門の横から、高3丈の長城に登り、
それより城壁の上の広さ15尺ないし20尺もある磚瓦の甬道を尾道伝いに西方の台に上る。
墩台は36丈毎に一つあって方形である、
第一の墩台には古銭やら数珠などを売っている乞食風のものがおったが、
第二の墩台の上には今朝北京を発して汽車でやってきた多くの外人、華人などが、盛んに食事を取っている。日本の大学生も見受けた。
いかさま見晴らしがよい。
南は山岳重疊の居庸関一帯をへて望京の情が起り、
北は山西北部の台地を越えて胡軍を呼ばう概がある。
形勢まさに天険である。
脚下を見ると石と磚とを漆喰で固めてある。
黄土と石灰と墨との三つを混じた三合土なるものを用いたというが
非常に堅牢にできて峰から峯へ延亘している偉観に、万里長城の名のふさわしきを思う。
ところどころに甬道から下りられる暗道がつけてある。
雉堞石のところどころ破れたるが惜しい気がする。
何にしてもかかる雄大なものが西は臨洮から東遼東に至る万余里に延亘したと思うと感慨無慮で、遠古の時代を回顧して默々たる思に沈むのも人情であろう。
しかし我等が今佇立して朔北の荒野に対しているこの城壁は決して一朝一夕にできたものでない。
上下三千年の間、漢民族の対外闘争の結果として、幾多英雄の心血を灑がしめたもの。
秦始皇がつくつたと簡単簡単な記述でかたづけてはすまないものである。
そもそも支那に長域のあるは必しも北に限らない。
今でも村落、県鎮すべて土垣または城壁をめぐらすように、洛陽あたりでは単に自己の田畑にさへ壘を繞らしている。
かような境界の観念は、紀元前4世紀戦国の世において著るしく列強の間に起り、
山東には斉斉魯の長城が泰山の左右に連り、河南に韓の長城ができ、
その南に楚の長城があるという風に、中原の間にあったが、
そのもっとも盛んに築かれたのは、何といつても北方の夷狄騎射に堪能なものを防がねばならぬ方面であつた。
すなわち直隷山西陜西の各省に国する所の燕、趙、魏、秦の四国はよほど早くからその工を起した。
それは西紀81年にローマ帝ドミティアヌスが、ライン、ダニューブ両岸河の間に長城<リメス>を築いて、北狄を限ったよりも、およそ500年も前の事で、
最初に、魏恵の恵王長城を固陽に築き、
ついで西暦前314年秦は義渠の戎を破って北地長城をつくり、
趙の武靈王は前307年林胡楼煩を破って代より陰山にかけて長城をつくり、
燕もまた東胡を破って造陽より襄平に至る長城を築いた。
いずれも夷狄を退けて漢民族の植民地を作くり、その当然の結果としての境界を守るためのものであるから、長城は前進的であり移動的であつた。
ゆえに秦が天下を一統するや、これら四国の跡をうけつぎ紀元前215年蒙恬をして北の方胡を討ちことごとく河南の地をとって直道を通じ、九原より雲陽に至る間、いわゆる東洋のローマンロードをつけ、長城は西臨洮より。東遼東まで万余里に達せしめた。
『匈奴伝伝』によるとこの時は「河によつて塞をつくったが、やがてまた河を渡り陽山北假中による」とあつて、
黄河の北の今の陰山々脈を越えて長城を広げたのであるから、実に前進的積極的である。
したがって漢民の力全く胡族を圧倒したので今日見るような堅固な城壁でなく、あるいは土壘、または石壘で比較的簡単な性質のものであったと見られるが、
その後漢民が到底北方の強勇に敵し得られぬやうになって、はじめて長城が消極的な防御機関となるに至り、山岳の険要によるところの蜿蜒としてつづく長城というものに進化した。
それは漢高祖が大同附近で匈奴の冒頓単干に囲まれた頃からの傾向である。
当時雁門の嶮によってこれを防御するにいたったのを、『史記匈奴伝』に
於是漢使三将軍軍屯北地、代屯句注、趙屯飛狐口、緣辺亦各堅守以備胡寇。又置三将軍、軍長安西細柳、渭北棘門、霸上以備胡。胡騎入代句注辺、烽火通於甘泉、長安。と記している。
この句注というは今の雁門関で飛狐口は恒山の北、いずれも内辺長城の要塞であるが、
屯兵が常にここを堅守し、胡人来るや烽火をもって長安に通知するという風の組織を完成したのである。
その後衛青のごとき武将が出ると、再び塞外に武威を揮うたけれども
爾来この受け身の防御壁としての性質が定まって、
五胡十六国の時代に胡人が北支那に侵入して王都を置く頃になっても、
やはりこの長城を重要なものとして、さらに後方に備える事になった。
~>゜)~<蛇足>~~
わかりやすくするため、原文の以下を変えました。
羅馬帝ドミチヤヌス: ローマ帝ドミティアヌス
西湖より包頭まで 6 包頭行 -03 居庸関
9月3日朝5時魁氏に起こされる。ここから居庸の四重の関を驢馬にて突破するのだから、ちと早起きを余儀なくされたのだ。
旅館を出て鉄道線路を西に横断し、南口河の河原の上をゆく、
暁風楚々気持ちがよい。
『水経註』に
「其水南流歴故関下、渓之東岸有石室三層、其戸牖扇悉石也。蓋故関之候台矣。南即絶谷、累石為関垣、崇墉峻壁、非軽功可挙。山岫層深、側道褊狭。」
とあるから、
西暦5世紀すでにここに山から山へかけて塁壁のあったのはたしかである。
この文中に古関と称するほどであるから、けだしよほど古い時代からのもので、
秦始皇がつくらしめた『呂氏春秋』にも、天下の九塞を挙げて居庸を記しており、
『淮南子』の「九塞」にも出ているから、この北方に通ずる関署はあるいは燕代にすでに設けられたにちがいない。
明代京師防備の第一線として古北口、居庸、紫荊の三つを特に重要視したのであるが、
元の大軍の勇猛をもってしても、金人のここを守るとき抜くことはあたわず、
嘉定二年には紫荊関から涿易二州に下り、それからこの南口に攻めて来たといい、
あるいはこの関所の東の松林の中の間道、わずかに一人しか通れないところを、元の太祖が通って南口に出て攻め上ったという伝説があり、
まことに天下の要塞燕王のいわゆる北平の噤喉であるから、永楽以後常に衛を置いたところである。
さてこの関所にはこの南口と八達嶺にある長城の関門すなわち北口とがあって、その南北二口の間に居庸関と上関があるから、合わせて居庸四関という。換言すれば長城の内側に三重の関所をつくり、各山から山へ取り巻いた定石をもっているのである。
南口の河原からこの左の山手の塁壁と、右の山手の墩台との間を進んでまず最初の城壁関門に達する。
この門を入ると古の南口市街で街並みの揃った20戸ほどの民家がある。
道路はすべて石畳であったのが、今はあれている。
『明史』の記すところにしたがえば、「南口城は洪武二年大将軍徐達の築くところ」とあるから『水経註』の作者の見た石塁ではないのであろう。
南口からさらに5支里をすすむと再び前面の山から山、谷から谷へ城壁が委蛇たるを見る。
これすなわち有名な居庸関で入口に穹門が二つ、一を通って右に曲がって第二門に入るとこれに「居庸関」と題してある。
穹門破れて危険だから、新道が外側を迂回してつけてある。
この門から行くこと1町にして道の中ほどに高3丈1尺の白大理石の穹門、道幅2丈4尺がある。
これは雲台または過街塔と称せらるるもので、元武宗が太后の寿福を祝して建てた塔で、
洞壁に釈迦像、金剛像などをはじめ、仏画やら漢、梵、蒙、回紇、女真の五体で呪文が刻してある。
洞道の両口にインドのガルタ像がほってある、彫刻の精巧真に驚くべきものがあるが、頂上の塔は今は烏有に帰し、道下の白大理石の敷石には風雨千年車軌の通った幅三寸深さ三寸ほどの轍跡がついていて、そぞろに懐古の情を呼ぶものがある。
茶店にてしばし休息してさらに進めば、街を離るるところにまた二つの穹門があって、また外方に「居庸関」と題してある。
この関をさると先カンブリア時代の片岩に代わるに花崗岩の噴出地となるから、
風蝕の結果両岸は秀峰壘起してまことに風景の妙を極める。
道路は荒れに荒れてまるで渓流である。
8支里を行くと第三の関門がある。
これを上関というが、その外方に「居庸外関」と記してある。
上関からさきは途いよいよ急に、渓谷ますます蹙まる。
谷に添うた旧道まったく破れて弾琴峡の方へ行けない。
しかたなくここで左方の山道を越える。
峠の下に五貴山隧道があるのだ。
この峠を越えて溪畔に出ると路傍に大きな岩がある。
これに二大字を題して「仙枕」とある。一大花崗岩である。
呂賁の隷書で非常に立派な字であるが、なおこの石には大行散人の詩、陽和の凱旋記などがほってある。
よく見るとこのあたりの路傍の花崗岩の少なく大なるものや断崖のところどころに種々の文書が刻してある。
いずれも能筆である。
石くれだった峡道をすすむと途中で奥地から馬群数10匹を率いた一隊に出会うこと2度、牛群にあうこと1度、いずれも手綱をかけていない。
2名ほどの牧夫の命に従って歩んでくる有様まことに温順なものだ。
馬を追うにはオウ、オウといい、牛にはチョツ、チョツと掛声している。
日本では馬にはドウ、ドウ、牛にはチョイ、チョイという。
なんだか似ているのも可笑しい。
やがて上関から17支里青龍橋村に達する。
これは北口の宿駅で、嶮崖によって作られた一山村であるが、
駅は右方の山腹に設けられている。
比較的豊かな住宅の2、3を見受けた。
この村からいよいよ八達嶺へ登るには、花崗岩の山道をおよそ3支里すすむのであるが、磊塊たる嶮坂である。
驢馬なればこそよくも登るものだと思う。
荒れた道を何度となく切りひらいたのであるからその切り下げた崖段が三つまでものこっている。すべり落ちたら大変だ。
ようやくにして八達嶺の関門に達する。
ここにも内外二重の門があって外門に「北門鎖鑰」の四大字がある。
まことにこれぞ華夷を限るの天嶮で有名な万里頂上に達したのである。
~>゜)~<蛇足>~~
わかりやすくするため、原文中以下を変えました。
前寒武紀 → 先カンブリア時代
西湖より包頭まで 6 包頭行 -02 明の十三帝陵
この旅館は我等が北支那にきて、はじめての支那宿だ。
一行に魁氏という50歳位な通訳をつれているのでこういう宿に入るのに都合がよい。
室は白壁で汚れもなく、鉄製の寝台があり、一人一室八畳敷位でなかなか気が利いている。
食事もオムレツ風のものや、肉の煮き合わせなどがあって不味くない。
ここで驢馬を雇う。蘇州の市場を思い出すが、鈴をかけていないのが淋しい。
12時に出発して途を東北にとる。
白河の上流がある。ここでは玉河という。
急峻な西山からにわかに平原に出るので非常な荒れ河で、
礫磧の河原がはなはだ広い。
旅宿のあるところもその河原の一部である。
一支里ほどをくると細流がある。
ここを横断すると高15メートルの断崖で、その上部は平坦な黄土の台地である。
このあたりでは黄土は必ずしも風積物たるの証を示さず、2、3尺の黄土層の、上にも下にも礫層がある。
河から登るときに黄土が四層、礫もまた四層で整合しているのを見た。
でその上部の黄土層が残っているところは農耕に適し、玉蜀黍、豆、粟などが見渡すかぎり穂波ゆたかであるが、
やがてこの第一層を失った礫層の土地にくると、柿や梨、林檎、桃などの果樹がつくってある。
南口駅で売る林檎は実にこのあたり一帯の礫層の産出であったのだ。
太平荘という村落に入る。
礫が多いから村界または戸界いずれも石垣をめぐらし、家屋は日乾瓦の方形土屋である。
さてこの村からさきも、同様な洪積層の波状地で、ここかしこに西山一帯の前衛として、陥没の名残をしめしている2、30メートルの円墳状の小丘がある。
先カンブリア時代の片岩に禿げたところは層向を明らかにしめしている。
こういう小丘の向側に、沙河の一大支流が一つの盆地を形成しているが、
その主山を天寿山といい、これを正面北において連山左にまわって右巻きになった全体の凹地を自然の兆域と見たて、
これに永楽以後の十三帝陵が配置されているので、規模の雄大なることおそらく天下第一の概がある。
正面に陵道の第一石房がある。
これは白大理石の精巧な牌楼で高3丈幅10余間。
もとは石を敷いた広い大道が南北に通じていたらしいが、
本年の洪水で流された跡を5支里ばかり行くと大紅門というがある。
ここからしばらく道路は荒れながら旧態にある。

3支里をへて聖徳功碑亭がある。
乾隆五十年明陵重修の際に刻した衰明詩が大理石の碑の裏面にある。
表面の碑文は明の仁宗の撰であるが、裏の方が書体遒勁を残している。
この碑亭に2箇の華表がある。

そこを出るとその北2支里ほどの間、石畳をしいた道の両側に石獣石人の列がある。
四獅、四豹、四駝、四象、四馬、十二文武官。
いずれも躯幹雄偉彫鏤精巧で、南京の孝陵のよりも景気がよい。
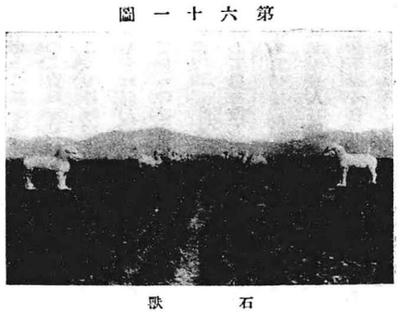
この列を過ぎると道まったく荒れている。
これは天寿山の西から出る沙河の氾濫の結果で、川幅数町磊々たる石河原と化し、過去の石橋の橋台のみ残っている。
これをわたり対岸台地の上にで10支里がほどをゆく。
なかなかひろい景色である。やがて長陵に達する。

すなわち永楽帝の陵墓であるが、陵外の対門を祾恩門といい、
そのなかにある重檐四翼229尺の大享殿を祾恩殿という。
これはまた驚くべき立派な建築材だ。
楠で径3尺6寸高さ5丈余の円柱32本、礎石1間以上の大理石の上に矗立している有様、
さすがに立派な殿堂で、見上ぐる天井の唐草模様から柱一面の漆ぬりなかなかの巨工である。
それが今は檐傾き雨漏り、殿上の神牌も破れている有様まことにもったいないと思う。
堂後白石三階の石段を下って、ずっと奥殿に入ると成祖文皇帝陵の大石碑があり、さらにその後ろに穹道がある。
歩して登れば、宝域に達する。穹道の上に楼をつくること南京孝陵に同じい、ここに立って宝域を見れば、松柏満山葱々たりである。
ここで再び帝王の尊厳を偲ぶ。
壁上に「明治十九年宇野哲人」、「大正四年荒木十畒」などと落書きがしてあるのを見る。
日本人の来るものけだしはなはだ多いのだ。
辞して勇を鼓してまた驢にのる。
実はさきに二回まで落ちたので、脾腿がややいたくなっているのだ。
帰途はかの石人石獣を見る要がないから、陵前1支里にして河を横ぎり西山に近づいて帰る。
途に崇陵の石壁を横ぎる。
往路4時間なりちも帰途3時間にして陂陀たる黄土と礫層との交互にでている台地をすぐれば、日ようやく没せんとして気力もやや飢えてきた。
しかし西山を背にしてこの洪積台地の突端からはるかに東南の低地を顧みるとき、雲煙縹緲、大洋に対するの感がある。
雄大の景致たしかに王者の兆域として天下に類なからんと思う。
南口につくと日まったく没して、街上カバコボと木魚を叩いて阿呆陀羅経節面白く奏するものあれば、路上土に坐して軍談読みにききとれているものもある。
言語の差異はあるが、調子は日本のそれとかわらない。
この国が本家だけに今に永続しているのだと聞きとれる。
~>゜)~<蛇足>~~
わかりやすくするため、原文中以下の地名を変えました。
前寒武紀 → 先カンブリア時代
~>゜)~<蛇足2>~~
私が初めて十三陵に行ったのは1983年。学校の遠足で行きました。
そのほか旅行客向けの一日観光などで行きましたがもっぱらバスで直行。
留学生の人たちの中には列車で行った人も。
いってみたらよかったなぁといまさらながらに思っています。

寒露の七十二候は
一候: 鴻雁来賓(鴻雁、来賓す)
二候: 雀入大水為蛤(雀、大水に入り蛤となる)
三候: 菊有黄華(菊に黄華有り)
鴈が北から群れでやってくる、雀をあまりみかけなくなる、菊が咲く季節です。
参考までに白露の日本の七十二候は
初候:「鴻雁来」(こうがんきたる)
次候:「菊花開」(きくのはなひらく)
末候:「蟋蟀在戸」(きりぎりすとにあり)
~>゜)~<蛇足>~~
「雀入大水為蛤」についてですが、
なぜ雀が蛤になると想像したのかというと、
寒くなってきたころ、雀を見かけなくなり、同じ時期に蛤がたくさん出てきたので、色柄がにていたこともあり、雀が蛤になったのだろうと、昔の人は考えたのだそうです。
寒露の画像は百度百科から





